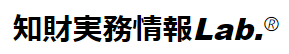田中 研二
田中 研二 ChatGPTでクレーム作成の練習をしよう!
こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二(弁理士)です。 突然ですが、私は素早いクレームドラフティングが得意ではありません。 発明ヒアリングをしながらサラッとクレームを書けるとカッコいいなあと思いつつも、恥ずかしながら、未だにその場でのクレーム作成にはもたつきますし、それよりも事前に提案書を読みながら時間を使ってクレームを用意するスタイルのほうが好きだったりします。 とはいえ、ヒアリングの場で次々に新しい情報が出てきたりすると、やはりその場で素早くクレームを作る...