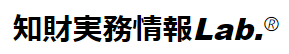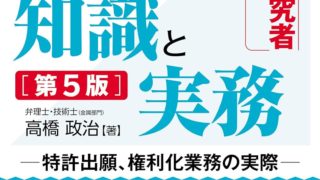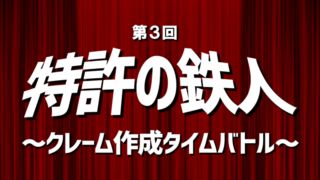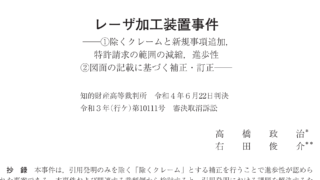高橋 政治
高橋 政治 (無料)第1回・特許の基礎知識【8/14開催セミナー】
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋です。 私の書籍「技術者・研究者のための特許の知識と実務(第5版)」を用い、この内容を解説するセミナーを開催いたします。 何回かに分けて、最初から順に、一通り解説していきたいと思っています。 ★第4版を用いて同様のセミナーを開催したのですが、第5版が出版されましたので、再度、開催したいと思います。最初に第4版と第5版との違いを説明する予定です。 「技術者・研究者のための・・・」とありますが、知財部や特許事務所に所属していてまだ経験...