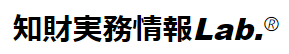高橋 政治
高橋 政治 中間対応において「除くクレーム」を検討するタイミングについて
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋(弁理士・技術士)です。 今回は中間対応において「除くクレーム」を検討するタイミング、すなわち、どのような場合に「除くクレーム」を検討することになるかについて書きたいと思います。 なお、以下では中間対応として「進歩性なしの拒絶理由通知書をもらったとき」について書きますが、「新規性なし」の拒絶理由通知書をもらったときも、ほぼ同じになると思います。 まずは、「進歩性なしの拒絶理由通知書をもらったとき」に、どのような思考手順で検討するか...